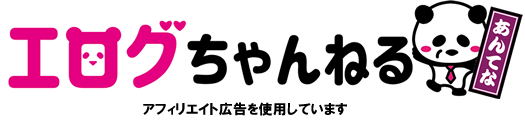愛が怒りに変わるとき 第1話

画像1枚
2025-02-16 14:50:00
「ちぇ、まだ帰ってないんかよ」もう7時を回ったというのに、肝心要言い出しっぺの梨沙の姿が見当たらない。 いつもならテーブル上に置いてあるはずの布巾や箸さえも無いまま忽然と姿をくらましていた。 敏則が唯一自慢できることといえば、梨沙は勤めが勤めであっても他家の違いちゃんと3度3度決まった時間に買ってきた総菜ではなく手作りのおふくろの味を提供してくれることだった。 叔母ではあるけれど母代わりの梨沙は、まどろっこしくはあったが、向かい合った席から性的な雰囲気をそれとなく味わわせてくれていた。 それが途切れた。 八時を過ぎ、九時まで待ったが帰ってこない。「あ~~ぁ、腹へったなぁ」人間飢えると性格まで変わる。 生まれてこの方台所仕事などしたことがないのに、なぜかこの日腹をへらして帰ってくるであろう叔母の分まで食事を作るんだと台所に立った。 冷蔵庫の中にあったタッパにお肉らしきものが入っている。「いい匂い。 うまそうだな、これにしよう」まさか下味をつけただけの豚のロース肉とは知らず、それをそのままさらに盛り付け、キャベツを千切りならぬみじん切りにし、添えた。 おかずはできたがご飯がない。 「まあいいや、こんだけ肉があんだから」贅沢すぎると自分自身に言い聞かせ、空きっ腹を満たすべく大口を開け放り込んだ。 が、見た目はともかくとても呑み込めたものではない。 良い香りと思っていた生にんにくの臭気にまずムカつく。 加えてヌルヌルしたラードの感触に吐き気をもよおした。 敏則はよゐこで通してきている。 吐き戻したりしたら叱られる、嫌われると、口に入れた分は顔をゆがめ呑み込んだ。 見つかる前にキャベツ混じりのすべての肉をタッパに戻し、またまた何気ない風を装い冷蔵庫にサッと仕舞った。―― あんだけのことをしてやったんだ ――敏則にとって、ヤラせてもらえまいかと、恥を忍んで初めて尽くす気になって調理めいたことをやった。 それが皿盛りだった。人は恋をすると優しくなれる。 失敗した肉を仕舞いながらもその肉を栞の秘部に見立て想った。 同時に与えてやれなかった己の股間を想いやった。 叔母に聞いてほしかった初となる異性への想い。 家ではいつも妖しげな姿を甥っ子に魅せ付け、楽しんでる。 あけすけなその、肝心の叔母が今夜はいない。 師匠で雇い主の栞と間一髪のところまで進み、中断させられただけに、その後間漢に面倒を看させたのではあるまいかとのが湧き、気持ちの持って行きようがなく自然、栞とキャバで働く叔母 梨沙の姿がダブり、姿を消した叔母への怒りにも似た心が初めてわいた。 思えば日を追うごとに栞が殊更優しく接してくれたのも、下心があってだったのだと気づかされ、落胆した。 とすれば、上のものを下にも置かない扱いをしてくれる梨沙こそ、甥で年下の自分への下心があったんじゃないかと思われ股間が疼いた。「ふたりとも俺とやりたかったってことか…」学業に専念しなければならないはずの敏則の頭の中は四六時中と言っていいほど学内の女の子に占領されていた。 化粧品の匂いからして股間によくなかった。 しかも目立つとか、きれいとか言われる女は、まるで競うように漢を漁ってて、時として校門に迎えに来させ、連れ立ってどこかに消えることもある。「おばさん、客の誘いに乗っちゃったのかなぁ…」JKですらエッチをやりたがるし、周囲の漢もそんな目で見る。 美人で、スタイル抜群の梨沙と行動を共にすると、どうしてもそんなことばかり考えてしまう。 そんな敏則をからかうかのように梨沙は、みだらな姿を惜しげもなく晒し、甥っ子をからかう。「あれが女の手かぁ…バカにしやがって」 漠然とした感触が、やがて行動へと変わっていった。 部屋を出た敏則の足は、まるで子が母の姿を追い求めるように表へと、噂に聞いた叔母の職場へとフラフラと彷徨い出た。 職場へは行きつけなかった。 なんとすれば、どうやって、どんなふうに口説いたら脱いで明け渡してくれるのか、思い浮かばない。「俺はまるで野良犬だ」鎖につながれ、発情した牝恋しさに吠え叫ぶ飼い犬。 が、鞭打たれることはあっても恋しい発情した牝のもとに愛を成就させてやるべく連れて行ってもらえるわけなどない。 それほど力が有り余ってるならと、逆に餌を減らされるのがおちだ。「自分だけ楽しんで、俺には飯も与えないってか」しがない画家の栞ならいざ知らず、漢どもに付け回されている叔母なら、必要とあらばいつでも抱いてもらえる。 ここ数日の叔母の様子から今がその時ではなかろうかと思え,腸が煮えくり返った。 敏則の中に、言いようのない怒りがこみあげてきた。「帰ってきたら鞭打ってやる!」犬を束縛している太くてボロボロの首輪が、重量物でも吊るすのかと思われるほどごついチェーンが頭の隅をよぎった。>