揺れる心 第2話

画像1枚
2025-01-11 17:22:48
「いる?」敏則が出かけた先は叔母の家から目と鼻の先にある工房だった。 栞はわざと陽当たりのよくない一室を借り切り、わずかでも光が差し込まないよう遮光カーテンを張り巡らせ、一日中同一の光の下で細やかなタッチの絵を描いていた。 長時間神経を張り詰めたまま描き続ける栞にとって、煩わしい雑事をこなしてくれる敏則は貴重な存在だった。 例えば絵筆ひとつとっても、使い終わる度に付着した絵の具を拭き取り、クレンジングで洗い、それをまた拭き取ったのちテレピンでクレンジング液を除去し、穂先を整え穂を下にして吊るし、次の工程に備える。「うん、来てくれたんだ。 じゃあシルバーとチタニウムを練っといてくれる」まばゆいばかりの光に満ちたアトリエで、更にデスクスタンドを使って手元を明るくし、小島栞は絵の一点をにらみつけていた。「はい、わかりました」言われた通り敏則は、紙パレット上にシルバーホワイトとチタニウムホワイトを等分量チューブから絞り出し、教えられたとおりの分量のリンシードオイルを瓶から注ぎ、ペインティングナイフを使って練り始めた。 叔母の家で下宿生活を送るというのは便利には違いないが、夜の仕事をしてまで養ってくれてることに敏則は後ろめたさを感じていた。 そんな折に見つけたのが、小さな折込広告だった。 学生のアルバイトは禁じられている。 が、個人的に手渡しで報酬をくれる画家さんのアトリエに入り込んでの手伝いなら見つからないだろうと面接に出向いた。 栞にとってもこれは好都合だった。 なぜなら彼女の最も不得手とするところのクロッキー、その中でも人体の骨格や筋肉の動きを写し取る解剖図だけは避けて通りたかった。 が、誰かに見られる心配のない自分のアトリエでなら、彼が石膏像代わりになってくれれば恥をかくことなく練習に没頭できる。 まことに助かるからだ。 初対面で相当驚いたような顔をされたが、無事雇ってもらえ、それ以降敏則は学校が終わるとここに入り込み、週に最低でも2~3回は通うようになっていった。「先生、こんな感じで?」栞から名前で呼んでいいと言われたが、雇い主でしかも年上、それも画家で身を立てるほどの腕前とあって、先生で通していた。 栞が敏則に名前で呼べと言いだしたのは、当初の目論見、モデルを務めさせてからだ。 敏則は、下手間作業も器用にこなしてくれたが、ことモデル業となると別格だった。 表情の豊かさに加え、鍛え抜かれた身体は画家という職業を忘れさせてくれるほど美しかった。 たちまち敏則がではなく、雇い主の栞が夢中になった。 デッサンに熱が入り、キャンバスとにらめっこ状態になると敏則は、そっと元居た場所を離れ栞の背後に立つようになっていった。 自分はどんな表情をしていたのか、気になるからだが「んっ!? ああ、疲れたのね。 少し休み入れましょうか」描きかけのキャンバスを、顔を赤らめ身体全体で隠そうとした。「変な顔してなかった、気になって」素直にこうつげる敏則に栞は「うん、いい感じ……よ」照れくさそうに笑った。 雇われた当初のころは文字通り下手間仕事だった。 それがいつの間にかモデルを仰せつかるようになっていった。 学生服のままモデルを務めていたものが上半身裸体に。 更に下半身もと、場の空気冠と言おうか次第次第にエスカレートしていった。 一流と呼ばれるまで画家は、自分の好きな題材を描けばよいというものではない。 食うために、頼まれたとあらば絵画教室の講師もこなさなければならない。 自分は風景画家だの、抽象画家だなどと、お金を頂いている以上言えた義理ではない。 どこで誰が見ているとも限らない。 高名な評論家に、場違いなギャラリーで批評されるかもしれない。 技術の幅を持つことも売名行為につながるからだ。「これまでずいぶん助けられたけど、敏則がいなくなると困るわね」栞は描きかけのキャンバスに目を落としながら言った。 下手間を、敏則がこなしてくれるから作業がはかどる。 それ以上に、敏則がいてくれるからやる気がわいてくる。 石膏デッサンなどというものは、気力が続かないことには上達しない。 その点でいうと、このところ栞の腕前はぐんぐん上達している。 その栞は敏則とひとまわり違う。 見た目より腕がモノを言う芸術家にあってか彼女は、ともすれば色気に走る芸術家仲間と違い、普段化粧もせず、長く伸ばした髪を無造作に後ろで束ね、年がら年中絵の具まみれの服を着、言葉遣いもお世辞にも良いとは言えない。 小柄だからかなおのこと小顔に見え、しかも大きな瞳が顔の大半を占めているようにも見え魅惑的で、その瞳に真正面から見つめられると、つい先ほどまでモデルを務めたおりも不用意にも下半身への意識を欠き、膨らませてしまい、そんな気持ちを悟られまいとするあまり彼女以上にどぎまぎした。 このようなどこか甘酸っぱい日々が、もう間もなく終わると思うと敏則の脳裏を一抹の淋しさが過ぎった。「本格的なマット・プレイなんか望んじゃいないよ。 あくまでもごっこだから」徹はそう諭すのだが、バイト先の女にすっかり心を奪われた同居といおうか、半ば同衾中の甥っ子のアトリエの女と織りなすいやらしい姿が頭の隅をかすめ、梨沙は聞く耳を持たなくなっていた。 それでもこんな時こそ漢がいてくれることがうれしいのか、梨沙はマット・プレイのまねごとを淡々と始める。 ローションを塗りたくってヌルヌルになったマット上に間男である徹は寝かされた。 梨沙はその背中に更にローションを垂らす。 そうしておいて、同じくローションまみれになった梨沙が覆いかぶさってきた。>
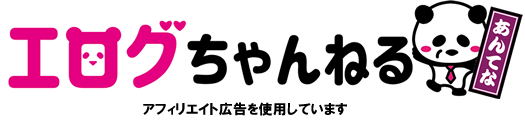















![[空の人動画]【某航空会社社員によるCA盗撮16】CAのスカートの中4日分<パンチラ盗撮>の画像](https://cdn.elog-ch.net/img_article/site/527/2026/01/31/19/w6IWusRxPd17698793441951_thumbnail250.jpg)



