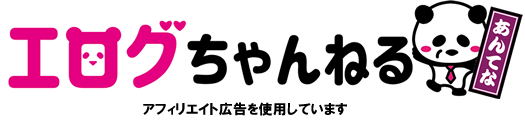愛が怒りに変わるとき 第4話

画像1枚
2025-03-16 16:11:30
思い込みの激しさを物語る睨みばしった顔つきと、独りぼっちになった時見せるそれとは真逆、叔母の梨沙をしてうろたえさせる、どこか憂いを秘めた仕草なのだ。 長年にわたって面倒見てきた梨沙にとって、敏則の考えていることなど手に取るようにわかる…はずであった。 日置徹に抱かれるまでは。 抱かれて初めて、自分自身の内に秘めていた何かに気づかされた。 すると、これまで見ようともしなかった甥っ子の心のうちが気になって仕方なくなった。(―― サカリがついた牡犬みたいに、四六時中ウチの尻を追いかけてたくせに。 このごろちっとも盗み見しなくなったと思ったら、恋してるような顔つき……でもまさか……)一時ではあるにせよ、一見の客と言っても差し支えない日置徹の、強引ともとれる告りに負け自分から進み出る形で深い関係になり、しかも胎内に残るその感触が忘れられず、よそよそしくなったオトコに、それでもヨリを戻せば肉欲に目覚めてくれるのではあるまいかと追いかけまわす。 女のサガを、それも外で恥ずかしげもなく女の大事な部分を魅せ付け迫り、なのに抱いてくれないことに怒り罵声を浴びせる。 キャバでは優等生であったはず…が、自宅に押し掛けたりすれば逆効果だとか、甥っ子の手前帰らねばならないことなど気にも留めなかった。(あの時彼が見せた、あの顔つきこそ今の敏則のそれ……)いつか自分が…そう想い続け、チャンスに恵まれず一日伸ばし二日伸ばししているうちにとうとう、敏則もまた相手を見つけ関係を持った。 いや、持とうとしてる。 そう思われてならなかった。「お店でナンバーワンの梨沙様も、これじゃ形無しね」箪笥の中に仕舞っていた下着類を全て出し、まさかに備え、奥に潜めておいたローターを取り出しスイッチを入れた。ぎこちない動きは、日置徹のソレとは比べ物にならないはずなのに、そんなものでもこの際と思わねばならないほど切羽詰まった梨沙は、自分でもなぜそんな行動に出たのか理解しがたかった。 下の口に指を這わせ、グニグニと蠢く先端を、すっぽりと咥え込んでいた。「あああ…ほ・し・い…コレが…硬いモノが……」長い間放置してたからだろう、電池が減り動きが鈍い。 その、弱く振動するローターを梨沙はためらいつつゆっくりパンティーの中央部に触れさせる。「あ、あああん、 もう、もう、敏則のチンポ……」恥じらいなどかなぐり捨て絶叫し、恋しい男の名を連呼していた。 乳首は尖り、パンティーのクロッチ部は漢どものチンポが侵入すべく探りを入れてきたとでも感じたのかぐっしょり濡れ、しかもしつこ過ぎたのか黒々とした恥毛がふたてに分かれ、隙間から肉芽までもが天を衝くほど腫れ上がりこぼれ出てきた。 両膝立ちになり、そっくりかえりながら押し当て続け、叶わぬ恋に狂うアソコを諫めた。(―― いけない、こんなところを見られたら……)立場が逆転する。梨沙はアソコに押し当てていたおもちゃを狂おし気に引き離し、汚れを舐めとり再び元のところに戻し、着替えの下着を取り出すと、家には自分しかいないのに何食わぬ顔をし浴室に向かった。 ドアを後ろ手で閉め、鍵をかけると脱衣所に置いてあった手鏡と剃刀を手に浴室に入り扉を閉め椅子には座らずしゃがむ形をとり、アソコを指で広げ手鏡に映し出し、興奮の度合いを調べにかかった。「敏則はコレを欲しがってる…こんな醜い形をしたココを……チンポならいざ知らず……」先妻の機嫌を損なうまいと忍んでいく亭主に、梨沙の母 秋乃はした。 修羅と化した母を見て育った梨沙はオンナにとって漢の何たるかを知っている。 母同様、漢欲しさに狂ってる証拠に、すっかり開門し、膣口の奥にあるピンクの媚肉がピクピクと脈打ち、チンポ欲しさからか犬や猫の上あごにある凸凹様に変化した膣壁が肉胴を、裏筋を舐め上げようと膣口に向かってせり出しては引っ込み、せり出しては引っ込みを繰り返していた。 引っ張り込むべく竿の滑りをよくするためか半透明の液体が膣奥から尻穴に向かって流れ落ちる。 こんなことではいけないと目を逸らしたその先に最前、徹に蹴られたときにできたであろう傷があった。 気持ちを落ち着かせるために脇を向いたのに、すっかり頭に血が上り、まるで逆効果になってしまった。 母 秋乃の場合、自傷行為で興奮を呼び覚ますというやつではない。 誰かに恐怖心を植え付けられると過剰反応が起きる。 その結果が性行為にまで現れる。 そんな母を見て育ってきたものだから、忌まわしい性癖が自分でも気づかないうちに生まれ育っていたというしかない。 好きになってしまった相手が既婚者と知った時にはもう母は、漢なしではいられない体になってしまっていたようなのだ。 何度別れを切り出したかしれないと、本妻のもとに走る亭主を見ては幾度も口にしたそうな。 に喚き散らすと、その都度漢を仕込まれ、とうとう我慢できなく…というより独り占めしたくなって離婚を迫りひと悶着ふた悶着やらかしやっと、正妻の座を射止めることができたという。 聞くに堪えられない罵声を浴びせられつつ抱かれているうちに母は、そうやって罵られないことには逝けなくなってしまったようなのだ。 梨沙はそんな母の性癖など知る由もないが…。 なのに、いつのころからか逆境という現象下でないと本気になれない自分がいることに気づき始めていた。 居竦むと修羅と化したオンナが頭をもたげ…というやつだ。>